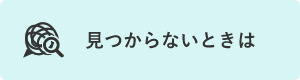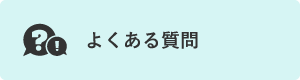農地中間管理事業による農地の貸借について
令和7年4月からの農地の貸借の方法が変わります
農地の貸し借りの手続には、これまで(1)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定、(2)農地中間管理事業による貸借、(3)農地法第3条に基づく貸借の3つがありましたが、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、(1)農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定が廃止されます。
今後は、(2)農地管理事業による貸借または(3)農地法第3条に基づく貸借で農地の貸借を行う必要があります。
農地中間管理機構(農地バンク)とは?
農地中間管理機構とは、都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織された法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで、「農地中間管理機構」となります。地域によっては、「農地バンク」「機構」「公社」などと呼ばれています。
県知事が指定した農地中間管理機構(ひょうご農林機構)は、農地の出し手と受け手の間に介在し、農地の貸し借りが円滑に進むよう調整する公的な機関です。
【洲本市版】農地中間管理事業パンフレット [PDFファイル/657KB]
手続きの流れ
以下の手順を経て、貸借が認可されます。
1.貸し手・借り手双方が必要書類を洲本市農政課へ提出
2.書類を洲本農地管理事務所へ送付し、洲本農地管理事務所にて審査会を開催
3.審査会を通過した後、洲本市農業委員会への意見照会
4.ひょうご農林機構との契約書(様式第11号・13号)が作成され、貸し手・借り手それぞれに送付
5.契約書にそれぞれが押印し、洲本市農政課へ提出
6.契約書を洲本農地管理事務所へ提出し、ひょうご農林機構から農用地利用促進計画の認可申請がされ、市が認可
7.契約書の写しが貸し手・借り手に送付される。
農地中間管理機構へ貸付けできる農地は?
●市街化区域外の田畑等であること。(洲本市は市内全域が対象です。)
※農用地等として利用することが著しく困難なもの、借受希望者が見込まれないものを除く。
(例:農業委員会で再生不能とされている遊休農地など)
●農用地等を貸し付ける期間は原則10年以上とする。
農地中間管理機構から農地を借り受けできる方は?
●地域計画が策定されている地域:目標地図に位置付けられた者等であること
●地域計画が未策定である地域:一定の要件を満たす、効率的・安定的な農業経営を目指している者 等
機構集積協力金
●地域集積協力金
地域で機構にまとまった農地を貸し付けた場合、その地域に対して協力金が交付されます。
●集約化奨励金
機構からの転貸または農作業受託により、農地の集約に取り組む地域に対して奨励金が交付されます。
よくある質問
Q1.賃料はどうやって決めるの?
→ 地域の標準的な賃料を参考にして双方の話し合いで決定します。使用貸借(無料)も可能です。
Q2.途中で解約することはできるの?
→ やむを得ない事情があり、出し手と受け手の双方が納得していれば中途解約が可能です。
Q3.契約期間中に耕作できなくなった場合はどうなるの?
→ 次の受け手がいる場合はその方に貸し付けます。1年間、次の受け手が見つからない場合は、出し手に農地をお返しすることになります。
Q4.借り手の見つからない農用地も貸すことができるの?
→できません。農地中間管理事業で貸借できる農地は貸し手と借り手の同意がある場合のみです。農地中間管理機構が借り手への農地の斡旋等を行うことはありません。
様式
貸付希望者(出し手)の方へ
貸付を希望される方は「貸付希望農地申出書」の提出が必要です。貸付には要件がございますので市農政課までご相談ください。
借受希望者(受け手)の方へ
農用地等の借受を希望される方は、「農用地等借受希望申込書」の提出が必要です。
・申請書等閲覧書(農業委員会提出用) [Wordファイル/17KB]
※新規就農者、新規参入事業者等については、上記以外に営農計画等の書類の提出が必要となりますので、農政課までご相談ください。