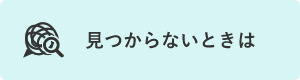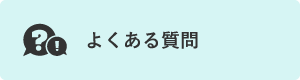国民健康保険税の軽減・減免
国民健康保険税(国保税)の軽減制度について
所得による国保税の軽減制度について
前年中の所得が一定基準以下の世帯は、国保税のうち均等割額と平等割額が軽減されます。軽減判定を行う際には、世帯の国保の被保険者のほか、特定同一世帯所属者※(旧国保被保険者)や国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)を含め、所得を判定します。ただし、前年中の所得がなくても、市県民税の申告をしていないと適用されません。判定は、賦課期日(4月1日)現在で行いますが、賦課期日後に世帯主が変わった場合は、変更後の世帯状況で再判定します。
※特定同一世帯所属者とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。(ただし、世帯の構成に変更があった場合は、特定同一世帯所属者でなくなります。)
軽減を受けるためには、洲本市が世帯主と国保加入者の所得の有無や扶養状況を把握する必要がありますので、前年1年間の収入がない方や、市外の人の扶養を受けている方は、必ず洲本市へ市県民税の申告をしてください。なお、この軽減を受けるための申請などの手続きは、必要ありません。
軽減が適用されるための条件(令和7年度分)
- 国保加入者(世帯主含む)全員の所得の合計が、軽減判定所得金額(※1)以下であること
- 洲本市が、世帯主と加入者の所得(扶養されている場合は、扶養されていること)を把握していること
| 軽減割合 | 軽減判定所得金額(※1) |
|---|---|
| 7割軽減 | 430,000円+{100,000円×(給与所得者等(※2)の数-1)} |
| 5割軽減 | 430,000円+(305,000円×被保険者数(※3))+{100,000円×(給与所得者等(※2)の数-1)} |
| 2割軽減 | 430,000円+(560,000円×被保険者数(※3))+{100,000円×(給与所得者等(※2)の数-1)} |
※1 所得金額とは、収入金額から控除額等(生活費を除く)を差し引いたものです。例えば、給与収入の場合、給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得金額です。
※2 給与所得または公的年金等に係る所得を有する方をいいます。
※3 特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)を含みます。
(注) 無収入の場合でも、必ず無収入であることを申告しなければ、軽減の対象とはなりません。市県民税の申告がお済みでない方は、印鑑を持って洲本市役所税務課までお越しください。
未就学児に係る国保税均等割額の軽減制度について
令和4年度の国民健康保険税より未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額について2分の1を減額します。また、所得による国保税の軽減制度が適用されている世帯の未就学児については、当該軽減適用後の均等割額を2分の1減額します。なお、この軽減を受けるための申請などの手続きは、必要ありません。
対象者
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
令和7年度分については、平成31年4月2日以降に生まれた方となります。
※未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
産前産後期間に係る国保税所得割額・均等割額の免除制度について
令和5年度(令和6年1月分)の国民健康保険税より出産被保険者の産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)の所得割額及び均等割額について、免除します。なお、この免除を受けるためには、申請が必要です。
対象者
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者
免除額
対象期間の所得割額及び均等割額
免除期間
出産日(出産予定日)の前月から出産日(出産予定日)の翌々月までの4か月間
※多胎妊娠の場合は出産日(出産予定日)の3か月前から出産日(出産予定日)の翌々月までの6か月間
免除申請について
下記の書類を持って、申請窓口にて申請してください。
(1)出産前に届出する場合
・届出書
・出産予定日を確認することができる書類
・単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
(2)出産後に届出する場合
・届出書
・添付書類不要
(ただし、出産被保険者と子が別世帯の場合は、出産日及び親子関係を明らかにする書類)
産前産後期間の国民健康保険税減額・国民年金保険料免除届出書 [PDFファイル/102KB]
申請窓口
・洲本市役所保険医療課
・洲本市役所五色庁舎窓口サービス課
・洲本市役所由良支所
自己都合によらず離職した方への国保税の軽減制度について
倒産・解雇など、自己都合によらず離職した方については、国保税が軽減されます。
対象者
令和6年3月31日以降に離職し、下記の1.か2.のいずれかに該当する方
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などにより離職した方)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどにより離職した方)
- 職業安定所(職安)から雇用保険受給資格者証を交付されていること。
(受給資格者証でも、特例受給資格者証、高年齢受給資格者証は対象外となります。) - 雇用保険受給資格者証に記載の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかであること。
軽減額
離職者の前年中給与所得を3割に減じて、国保税額を計算します。
軽減期間
令和6年3月31日から令和7年3月30日までに離職した方 令和7年度中
令和7年3月31日から令和8年3月30日までに離職した方 令和7・8年度中
の間、国保税額が軽減されます。
軽減申請について
自己都合によらず離職した方への国保税軽減制度を受けるためには、申請が必要です。
雇用保険受給資格者証と本人確認書類を持って、以下の窓口にて申請してください。
申請窓口
- 洲本市役所税務課
- 洲本市役所五色庁舎窓口サービス課
- 洲本市役所由良支所
国保から後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減について
平成20年4月以降、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行しました。それにともなって、国保に引き続き加入する方の国保税負担が急に増えることのないように、国保税の軽減措置を設けています。
単身世帯となる場合の国保税の軽減について
後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、国保被保険者が一人の世帯となる場合には、国保税の医療分及び後期高齢者支援金分に係る平等割が5年間は2分の1が軽減され、その後、3年間は4分の1が軽減されます。
今までの国保税の軽減について
軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(特定同一世帯所属者)については、今までと同様の軽減判定がされるよう、その方の所得・人数も含めて軽減判定されます。
国保税の減免について
国保税の減免制度は、災害や失業などにより国保税を納めることが困難になった場合に、申請により国保税を減免する制度です。
減免に該当する理由
下記の理由により、減免を申請することができます。
- 失業または事業の休廃止により、収入が著しく減少し、納税が困難なため。
- 納税義務者等が死亡・疾病等により、納税が困難なため。
- 災害等により自己の財産等に被害を受け、納税が困難なため。
- 75歳の誕生月を迎える方が、会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である方(65~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合(下記参照)
- 前記のほか、特別な事情があると認められる場合。
※ 減免申請後、生活状況・収入状況等を調査のうえ、該当するか否かを審査します。
※ 詳しくはこちらをご覧ください。
洲本市国民健康保険税の減免に関する規則 [PDFファイル/168KB]
国保から後期高齢者医療制度への移行に伴う減免について
75歳以上の方が、被用者保険(社保・健保など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合、新たに国保税を負担することになるため、下記のとおり減免制度の適用を受けます。
所得割の減免について
75歳以上の方が、被用者保険(社保・健保など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満の方のみ)が国保へ加入する場合、被扶養者の所得割を全額免除します。
均等割の減免について
75歳以上の方が、被用者保険(社保・健保など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満の方のみ)が国保へ加入する場合、加入した月以後2年間、被扶養者の均等割を半額免除します。(ただし、7割、5割軽減を受ける世帯を除きます。)
平等割の減免について
75歳以上の方が、被用者保険(社保・健保など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳以上75歳未満の方のみ)が国保へ加入する場合、後期高齢者医療制度に移行した方とその被扶養者のみで構成された世帯の場合は、国保加入した月以後2年間、平等割を半額免除します。(ただし、7割、5割軽減を受ける世帯を除きます。)
※世帯の軽減判定の際には、減免を受ける者の所得も判定の対象となります。
減免期間の変更について
平成31年度から均等割・平等割の減免適用期間が見直され、「国民健康保険の資格取得日が属する月以後2年を経過する月までの間」に限り適用されます。
今回の見直しは、すでに国民健康保険の資格取得している旧被扶養者の方も対象となりますので、平成29年4月以前に資格を取得している旧被扶養者については、平成31年4月以降均等割額・平等割額の減免は適用されません。
減免申請について
国保税減免制度を受けるためには、申請が必要です。必要書類をお問合せのうえ、以下の窓口にて申請してください。
申請窓口
- 洲本市役所税務課
- 洲本市役所五色庁舎窓口サービス課
- 洲本市役所由良支所