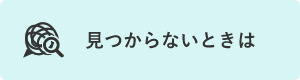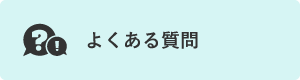国民健康保険税の税額計算
税額計算から通知まで
1.4月から翌年3月までの年間国保税額を、医療分、後期高齢者支援金分、介護分について下記の税率表で計算します。税額は、
国民健康保険税 = 医療分 + 後期高齢者支援金分 + 介護分
となります。
2.年度の途中で加入するなど、12か月加入しない場合は、年間国保税額を月割りします。
3.住民票(世帯)が同じ「加入者全員」の国保税を、住民票上の「世帯主」宛てに通知します。(世帯主が国保に加入していなくても同様です。)
税額(率)表(令和7年度分)
税額(率)表の項目については、下記のとおりです。
(※平成30年度より資産割を廃止し、賦課方式を所得割・均等割・平等割の「3方式」へ変更しました。)
- 医療分 加入者全員
- 支援金(後期高齢者支援金)分 加入者全員 ※ 平成20年度に医療分から分かれました。
- 介護分 40歳以上65歳未満の加入者のみ
・平等割 一世帯にかかる税額
・均等割 加入者一人ひとりにかかる税額
・所得割 加入者の所得に応じてかかる税額
医療分
| (1)平等割(一世帯にかかる税額) | 19,000円 |
|---|---|
| (2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) | 28,000円×加入者人数 |
| (3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) | 基準総所得金額(*)×7.0% |
| 医療分年間国保税額 |
(1)平等割+(2)均等割+(3)所得割 ※最高限度額:660,000円 |
後期高齢者支援金分
| (1)平等割(一世帯にかかる税額) | 7,500円 |
|---|---|
| (2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) | 11,000円×加入者人数 |
| (3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) | 基準総所得金額(*)×3.0% |
| 後期高齢者支援金分年間国保税額 |
(1)平等割+(2)均等割+(3)所得割 ※最高限度額:260,000円 |
介護分
| (1)平等割(一世帯にかかる税額) | 5,500円 |
|---|---|
| (2)均等割(加入者一人ひとりにかかる税額) | 11,800円×加入者人数 |
| (3)所得割(加入者の所得に応じてかかる税額) | 基準総所得金額(*)×2.7% |
| 介護分年間国保税額 |
(1)平等割+(2)均等割+(3)所得割 ※最高限度額:170,000円 |
* 基準総所得金額とは、 所得の合計から基礎控除額を差し引いた金額をいいます。
基礎控除額は、合計所得金額により下表のとおりとなります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
所得割の計算について
所得割計算の対象となる所得
加入者が前年中に得たすべての所得の金額です。ただし、退職金、遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給付金等は含まれません。
所得から控除される額
医療分及び後期高齢者支援金分は、加入者全員の所得からそれぞれ基礎控除額を差し引いた額の合計金額が基準総所得金額になります。介護分は、介護保険第2号被保険者に該当する方の所得から基礎控除額を差し引いた額の合計額が介護分の基準総所得金額となります。国保税には、住民税のような扶養控除、社会保険料控除等はありません。
後期高齢者医療制度が始まってから変わったこと
後期高齢者支援金分
平成19年度までの医療分が、平成20年度から医療分と後期高齢者支援金分とに分かれました。
平等割の軽減
国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国保被保険者が1人となった世帯について、医療分・後期高齢者支援金分の平等割が5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。
被扶養者だった方の保険税の軽減
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳~74歳)が新たに国保に加入した場合、申請により減免が受けられます。
*平成31年度から均等割・平等割の減免適用期間が見直され、「国民健康保険の資格取得日が属する月以後2年を経過する月までの間」に限り適用されます。
今回の見直しは、すでに国民健康保険の資格取得している旧被扶養者の方も対象となりますので、平成29年4月以前に資格を取得している旧被扶養者については、平成31年4月以降均等割額・平等割額の減免は適用されません。なお、所得割額に係る減免期間については当分の間、期間制限はありません。