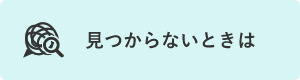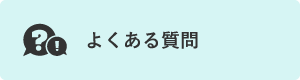マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療)
⇒国民健康保険のマイナンバーカードの保険証利用は、「マイナンバーカードの健康保険証利用について(国民健康保険)」をご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードが健康保険証として、ほとんどの医療機関や薬局の窓口(一部未対応)で利用できるようになりました。
従来の健康保険証についても、これまでどおり使用することができます。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。
登録方法については、以下のとおりです。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う。
- 「マイナポータル」から行う。
- セブン銀行ATMから行う。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご覧ください。
また、利用できる医療機関・薬局や開始時期については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>をご覧ください。
●マイナンバー法等の一部改正法により、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
令和6年12月2日以降、被保険者証は発行されなくなりましたが、マイナ保険証(保険証利用登録後のマイナンバーカード)または資格確認書で、医療を受けることができます。
●資格確認書の交付について
令和6年12月2日から令和8年7月31日までの暫定運用として、 後期高齢者医療制度加入者で、新たに資格を取得する、または資格情報に変更があったなどの場合は、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
【令和7年8月の年次更新について】
後期高齢者医療制度加入者には、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
⇒資格確認書の詳細については、「後期高齢者医療資格確認書について」をご覧ください。
●マイナ保険証を利用することで、次のような証類について、医療機関等の窓口で提示が不要となります。
・保険者証類(後期高齢者医療被保険者証)
・後期高齢者医療資格確認書
・限度額適用・標準負担額減額認定証(※)/限度額適用認定証 (オンライン資格確認導入済みの医療機関等のみ)
など
(※)長期入院該当の申請について(低所得IIの所得区分)
過去12カ月の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、別途「長期入院該当」の申請が必要になります(オンライン資格確認を受ける場合も、申請が必要となります)。なお、加入する保険者(国民健康保険や会社の健康保険など)に変更があった場合は、変更前の入院日数(低所得IIの認定を受けていた期間)を合算することが可能です。
【マイナ保険証を使うメリット】
●より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
詳しい内容は、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について(後期高齢者医療)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望される場合、申請により解除することができます。
●本人が解除申請する場合
本人(被保険者)のマイナンバーカードを持ってきてください。
●代理人が解除申請する場合
次のものをそれぞれ持ってきてください。
・本人(被保険者)のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人が親族以外の場合は、本人からの委任状も必要です。
【注意事項】
利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、2か月程度時間がかかります。